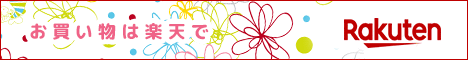ジムニーにオーバーフェンダーを装着している、あるいはこれから取り付けたいと考えている方にとって、「捕まるリスクはあるの?」「構造変更しないと車検に通らない?」という疑問は避けて通れません。
特にJB23やJB64オーナーにとって、9mm幅のフェンダーならOK?という話題はよく耳にするのではないでしょうか。
実際のところ、保安基準を超えたまま公道を走行すれば、違反で処分される可能性もあります。車幅がわずかに変わるだけでも、軽自動車規格から外れてしまうことがあるため、カスタムには慎重さが求められます。
この記事では、「構造変更の要否や公認取得の費用」、「車検時にフェンダーを外すべきか」、「自作フェンダーは通るのか」といったポイントを詳しく解説します。
安心してカスタムを楽しむためにも、正しい知識を身につけておきましょう。
この記事でわかること
- 装着時の違反とされる条件
- 構造変更が必要になる全幅の増加基準と費用
- 車検に通すために取り外すべきかの判断基準
- 車検対応フェンダーの選び方
ジムニーオーバーフェンダー車検の基礎知識

- ジムニーでオーバーフェンダーは捕まる?
- 構造変更が必要なケースとは
- 車検時にオーバーフェンダーを外すべきか
- JB23車検対応のオーバーフェンダーとは
- 公認取得にかかる費用の目安
ジムニーでオーバーフェンダーは捕まる?
ジムニーにオーバーフェンダーを装着した場合、違法な状態であれば取り締まりの対象になる可能性があります。
違反の主な理由は、フェンダーの幅が保安基準を超えてしまうことにあります。
特に、車両の全幅が基準値を超えている場合や、構造変更や公認申請をしていないまま公道を走行している場合は、整備不良や保安基準不適合として処分されることがあります。実際、軽自動車規格であるジムニーに大幅なオーバーフェンダーを取り付けたまま走行すると、車幅が規格を超えてしまうケースが見られます。
例えば、構造変更せずに片側10mm以上のフェンダーを追加すると、合計20mm車幅が広がることになり、軽自動車の規格(全幅1,480mm以内)を超えてしまうことがあります。これが発覚した場合、違反として「整備命令書」が交付される可能性もあります。
構造変更が必要なケースとは

構造変更が必要となるのは、車両の寸法や重量、乗車定員、用途などに変更が加わる場合です。ジムニーにオーバーフェンダーを装着する場合も、全幅が20mm以上広がると構造変更の対象になります。
これは道路運送車両法によって定められており、構造変更をしないままその状態で車検を受けようとしても、通過できない可能性が高いです。また、公道での走行そのものが違反とみなされる場合もあります。
例えば、JB64ジムニーは標準で全幅1,475mmとなっています。ここに片側10mmのオーバーフェンダーを付けた場合、合計1,495mmとなり、軽自動車の規格(1,480mm)を超えてしまいます。このようなケースでは構造変更を行い、普通車として再登録する必要があります。
ただし、9mm以下のオーバーフェンダーであれば、全幅の変化が20mm以内に収まり、構造変更を避けられることもあります。装着前に寸法の計算と保安基準の確認を行うことが大切です。
車検時にオーバーフェンダーを外すべきか
オーバーフェンダーの仕様によっては、車検時に取り外すことが推奨されます。特に、保安基準に適合していない場合や構造変更手続きを行っていない場合は、そのままでは車検に通らない可能性があるためです。
仮に、普段は取り付けていても、車検の際に一時的に外してノーマル状態に戻すことで、通過できるケースもあります。ただし、これは本質的な解決策ではありません。というのも、車検通過後に再び違法な状態で公道を走行すれば、やはり違反となるためです。
一方で、車検対応のオーバーフェンダーを選んだり、構造変更や公認取得を事前に済ませておくことで、わざわざ外す必要がなくなります。費用や手間はかかりますが、安全かつ合法的にカスタムを楽しむためには、適切な対応を取ることが重要です。
JB23車検対応のオーバーフェンダーとは

JB23ジムニーにおいて車検対応とされるオーバーフェンダーとは、国の定めた保安基準を満たした製品のことを指します。具体的には、取り付け後の全幅が1,480mm以下であることが重要です。
JB23は軽自動車の規格内で設計されているため、オーバーフェンダーの幅が片側9mm以下であれば、多くの場合、全幅が規格を超えることはありません。この「片側9mm」というサイズは、車検対応の目安としてよく取り上げられます。
例えば、市販されている「JB23専用の9mmオーバーフェンダー」は、フェンダーアーチにぴったり合う形状で作られており、取り付けても寸法オーバーになりにくいため、ユーザーの間で人気です。さらに、製品によっては「車検対応」と明記されており、安心して使用できます。
ただし、すべての製品が公認を受けているわけではありません。メーカーが「車検対応」としていても、取り付け方や他のカスタム内容によっては基準を超えてしまうこともあるため、購入前には必ず寸法を確認し、必要であれば整備工場などでチェックしてもらいましょう。
公認取得にかかる費用の目安
ジムニーでオーバーフェンダーを公認取得する際には、構造変更手続きが必要になります。費用は手続きの方法や依頼先によって異なりますが、おおよその相場は以下の通りです。
まず、構造変更に必要な書類作成や手数料として、自分で陸運局へ申請する場合は2,000円〜5,000円程度の手数料が発生します。しかし、多くの場合、整備工場や専門の業者に依頼することになるため、その分の工賃や手数料が加算され、全体で2万〜5万円ほどが一般的な目安となります。
さらに、検査に合格するためにはトレッド計測やヘッドライト光軸調整など追加作業が発生することもあり、その場合はさらに数千円〜1万円程度が加算されることもあります。
例えば、構造変更と同時に車検も依頼するケースでは、車検費用と合わせて7万〜10万円ほどになることも少なくありません。もちろん、車両の状態や地域、業者の方針によって前後します。
このように、カスタム後も合法的に走行を続けたいと考えるのであれば、公認取得の費用を事前に見積もり、信頼できる整備工場に相談してみることが大切です。
ジムニーオーバーフェンダー車検の対策と選び方

- jb64にオーバーフェンダー9mmはOK?
- 自作オーバーフェンダーは車検対応可能?
- 構造変更せず車検を通すには?
- 公認取得の流れと手続き方法
- おすすめの車検対応パーツまとめ
- 車検に通る幅の基準を再確認
jb64にオーバーフェンダー9mmはOK?
JB64ジムニーに片側9mmのオーバーフェンダーを装着することは、多くの場合、軽自動車の規格内に収まるため車検に通る可能性があります。これは、全幅の増加が合計18mm以内に収まり、構造変更の対象とならない点がポイントです。
具体的には、JB64ジムニーの全幅は標準で1,475mmとなっており、片側9mmのオーバーフェンダーを取り付けた場合でも全幅は1,493mm。軽自動車の上限である1,480mmは超えてしまいますが、構造変更が必要となる基準は「20mm以上の増加」とされているため、グレーゾーンに位置します。
このため、製品によっては「車検対応」とされているものもあります。ただし、取り付け方が雑だったり、他のカスタムと組み合わせて幅がさらに広がってしまうと、基準オーバーと判断されることがあります。
安心して使用するためには、事前にフェンダーの寸法や取り付け方法を確認し、できれば整備士などの専門家に相談することをおすすめします。
自作オーバーフェンダーは車検対応可能?

自作のオーバーフェンダーでも、保安基準に適合していれば車検に通る可能性はあります。ただし、手作りという特性上、検査官の目が厳しくなる傾向があるため注意が必要です。
主に確認されるのは、全幅の変化・取り付けの強度・角の処理(鋭利でないこと)・素材の安全性などです。これらが基準を満たしていれば、必ずしも「既製品でなければいけない」というルールはありません。
例えば、樹脂製の自作フェンダーをボディにしっかりと固定し、出幅が適正であることを証明できれば、整備工場でも通過実績がある事例は存在します。ただし、寸法が20mm以上広がると構造変更が必要となるため、自作でそのラインを超えないよう正確な計測が重要です。
また、見た目の仕上がりも車検の印象に影響するため、工作精度にも配慮したいところです。市販のフェンダーより難易度は高いですが、工夫と準備次第では合法的に使用できます。
構造変更せず車検を通すには?
構造変更を行わずに車検を通すためには、カスタムによって車両の基本寸法や性能に大きな影響を与えないようにすることが求められます。オーバーフェンダーの場合は、特に「全幅が20mm以内の増加であること」が重要です。
この基準を超えると、構造変更の手続きが必須になります。一方、20mm未満の変化であれば、通常の継続検査として車検を受けることが可能です。そのためには、フェンダー自体の出幅だけでなく、ホイールのオフセットやタイヤのはみ出し具合にも注意を払う必要があります。
例えば、片側9mmまでのオーバーフェンダーにとどめ、ホイールを純正やそれに近いサイズにすることで、車検に問題なく通る構成が実現できます。また、フェンダーの取り付けがしっかりしており、安全性に問題がないかどうかも確認ポイントになります。
このような条件をすべてクリアすれば、構造変更を避けた状態でも車検を通すことは可能です。ただし、不安がある場合は整備工場で事前に確認してもらうことが安心です。
公認取得の流れと手続き方法
ジムニーにオーバーフェンダーを装着した場合、特に車幅が増加するようなカスタムでは「構造変更」が必要になるケースがあります。
この構造変更の一環として行うのが「公認取得」の手続きです。ここでは、その具体的な流れと必要な準備についてわかりやすく解説します。
公認取得とは何か?
公認取得とは、カスタムした車両の仕様を正式に車検証へ反映させるための制度です。これを行うことで、改造後の状態でも合法的に公道を走行できるようになります。
最初に行うべきこと
まずは、装着したオーバーフェンダーによって全幅がどれだけ変わったのかを確認しましょう。全幅が20mm以上増加している場合、構造変更の対象になります。その場合、公認取得の手続きが必要になります。
構造変更の申請方法
構造変更を行うには、管轄の運輸支局に「構造等変更検査申請書」や、必要な図面・寸法データなどを提出し、検査予約を取る必要があります。これらの書類は正確に記入しなければならず、不備があると検査を受けられないこともあります。
検査当日のポイント
実際の検査では、車両の全幅・全長・全高のほか、車軸位置や灯火類の配置など、保安基準への適合性が細かく確認されます。オーバーフェンダーについても、しっかりとボディに固定されており、外れたりしない構造であることが求められます。
車検と同時に行うことも可能
この構造変更は、車検のタイミングに合わせて行うことも可能です。その場合、通常の継続検査と構造変更の両方が同時に実施されます。必要書類も併せて提出するため、手続きが効率的になります。
手続きに不安がある場合は?
初めて構造変更を行う方や書類作成に自信がない場合は、整備工場やカスタム専門ショップに代行を依頼するのも一つの方法です。費用は発生しますが、スムーズかつ確実に公認取得を進められるというメリットがあります。
おすすめの車検対応パーツまとめ

車検対応のオーバーフェンダーを選ぶ際は、見た目だけでなく「基準を満たしているか」が最も重要なポイントです。ここでは、ジムニーに装着可能なおすすめの車検対応パーツをいくつか紹介します。
まず、JB23やJB64向けに販売されている「片側9mmオーバーフェンダー」は非常に人気があります。このサイズは構造変更不要の範囲内で収まるため、比較的安心して取り付けることができます。中でも、ABS樹脂製やゴム素材の製品は軽く、柔軟性も高いため扱いやすいです。
他にも、ボルトオンで簡単に取り付けられるタイプや、フェンダーアーチのラインに合わせた純正風デザインのものもあり、見た目と実用性のバランスを取りたい人におすすめです。
一方で、海外製の大きなフェンダーや安価なノーブランド品は、車検非対応となる可能性もあります。購入前には必ず「車検対応」の記載があるか確認し、信頼できるメーカーから選ぶようにしましょう。
車検に通る幅の基準を再確認
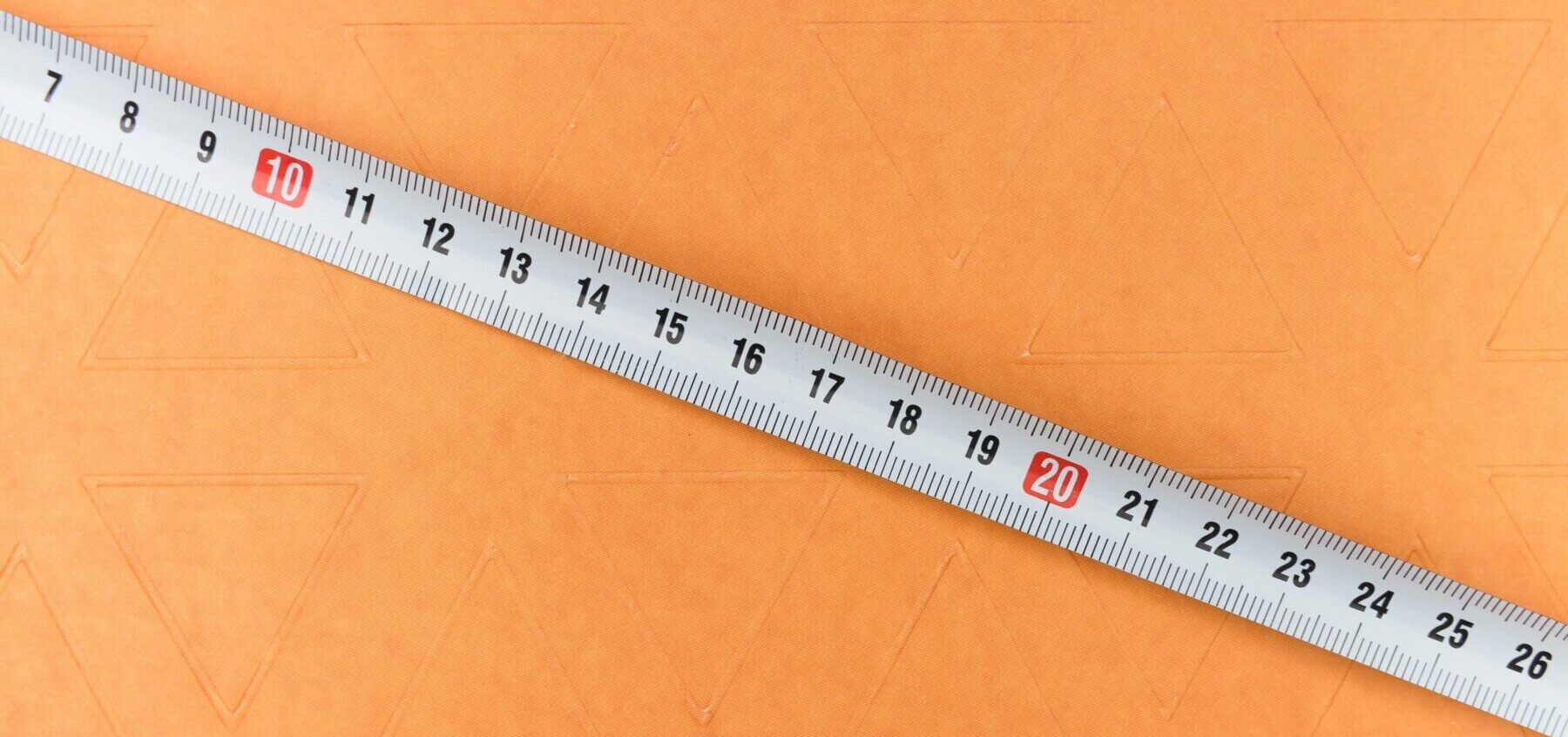
オーバーフェンダーを取り付ける際、車検に通るためには「全幅がどれだけ増えてよいのか」という基準を把握することが大切です。ここで改めて、その幅に関する基準を確認しておきましょう。
保安基準では、車両の全幅が「改造前から20mm以上増加した場合」は構造変更が必要とされています。つまり、片側10mmを超えるオーバーフェンダーを装着することで、構造変更の対象になる可能性が高まります。
例えば、JB64ジムニーは標準で1,475mmですので、片側9mm(合計18mm)のオーバーフェンダーであれば、全幅は1,493mmとなり、構造変更の範囲外に収まります。しかし、他のカスタムによって幅がさらに増す可能性もあるため、実際の寸法を必ず測る必要があります。
また、フェンダー自体の出幅だけでなく、タイヤやホイールのはみ出しがある場合も、幅の測定結果に影響します。見た目では分かりにくいため、ノギスやスケールを使って正確に測定しましょう。
ジムニーオーバーフェンダー車検のポイントまとめ
記事のポイントをまとめます。
- オーバーフェンダーの装着で捕まる可能性があるのは保安基準違反時
- 全幅が20mm以上広がると構造変更が必要
- 軽自動車の全幅上限は1,480mmまでと定められている
- 構造変更なしで片側9mmまでのフェンダーなら対応しやすい
- JB23用には車検対応を明記した9mmフェンダーが多い
- JB64では全幅1,493mm以内ならグレーゾーンで済むことがある
- 自作フェンダーでも基準を満たせば車検に通る可能性がある
- 車検時は違法性のあるフェンダーは取り外すのが安全
- 構造変更の手続きは運輸支局への申請と現車検査が必要
- 公認取得にはおおよそ2万〜5万円の費用がかかる
- 検査ではフェンダーの取り付け強度や安全性も見られる
- 車検と構造変更は同時に行うことも可能
- タイヤやホイールのはみ出しも幅の測定に影響する
- フェンダー選びは「車検対応」と明記された製品が無難
ジムニーのタイヤサイズの限界と安全にカスタムする方法を解説